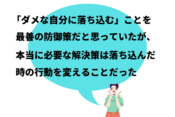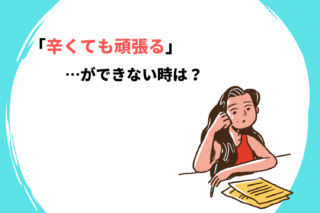全か無か思考とは?落ち込みにくい柔軟な考え方に修正する方法を紹介
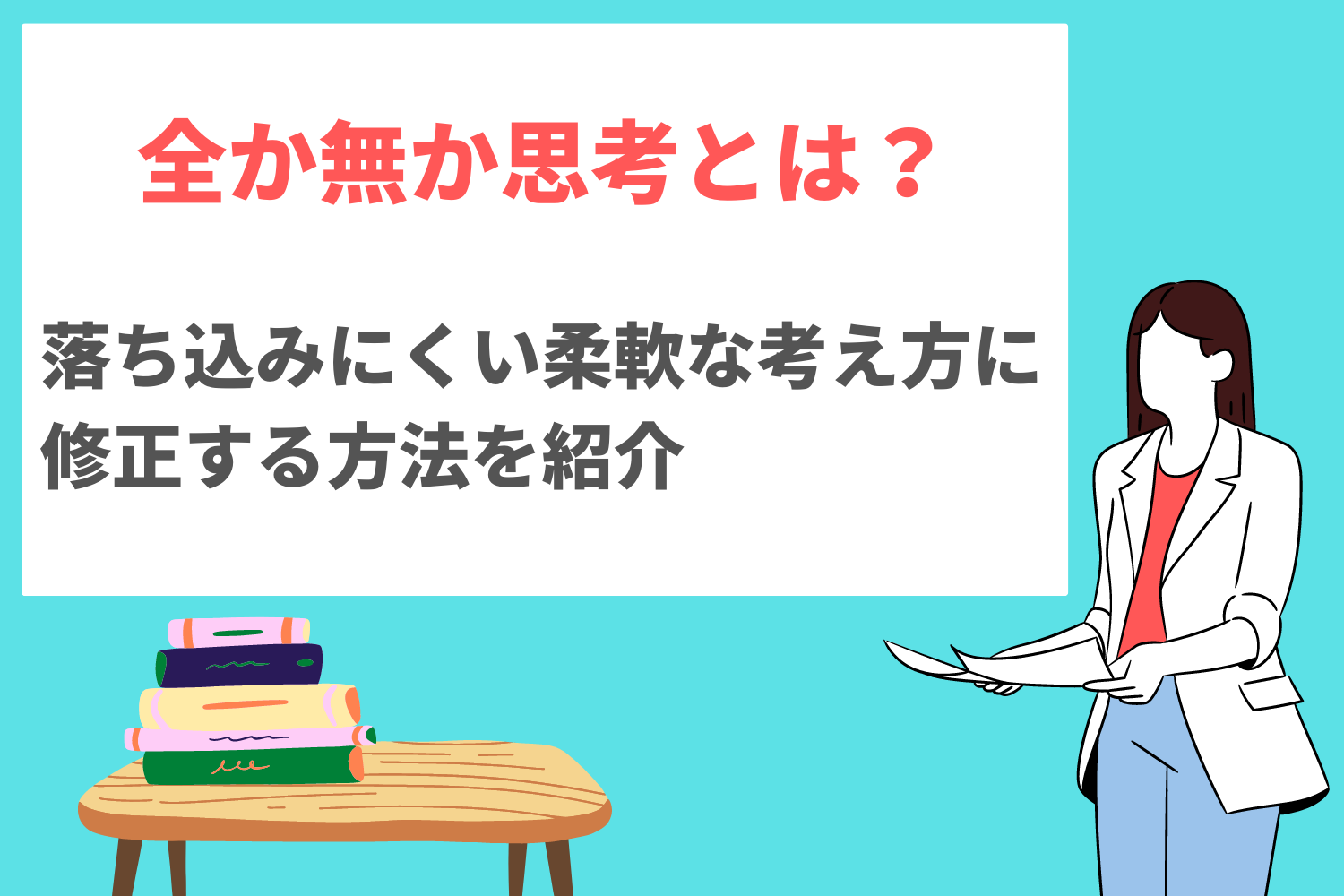
「全か無か思考」とは、物事を0か100かで考える思考パターンです。
心理学では、全か無か思考を「認知の歪み」と言い、修正したほうが良い考え方のひとつとしています。
落ち込みやすい性格の人であれば、全か無か思考を修正し、柔軟な考え方ができるようになりたいと思うはず。
ここでは、全か無か思考の意味を説明するとともに、自分でできる思考パターンを修正する方法について、お伝えします。
目次
全か無か思考とは?
少しのミスでもあれば、すべて失敗してしまったように捉えてしまう…
このような極端な物事の捉え方を、心理学では「全か無か思考」と言います。
認知行動療法の先駆者で、アメリカで活動する精神科医 デビッド・d・バーンズ医師は、全か無か思考を著書のなかで次のように定義しています。
「ものごとを白か黒のどちらかで考える思考法。少しでもミスがあれば、完全な失敗と考えてしまう。」
(引用 デビッド・d・バーンズ(2013):いやな気分よ さようならコンパクト版.星和書店)
例えば、仕事で些細なミスをしたとしましょう。
それを全か無か思考で捉えると、「ミスをするなんて、会社の足を引っ張る使えない人材だ」といったように、おかしたミス以上の評価を自分にくだしてしまうのです。
100点以外は、すべて0点。
本当なら間の点数もあるはずなのに、なぜかそれを無視して、物事を極論で捉えてしまうのが全か無か思考の特徴です。
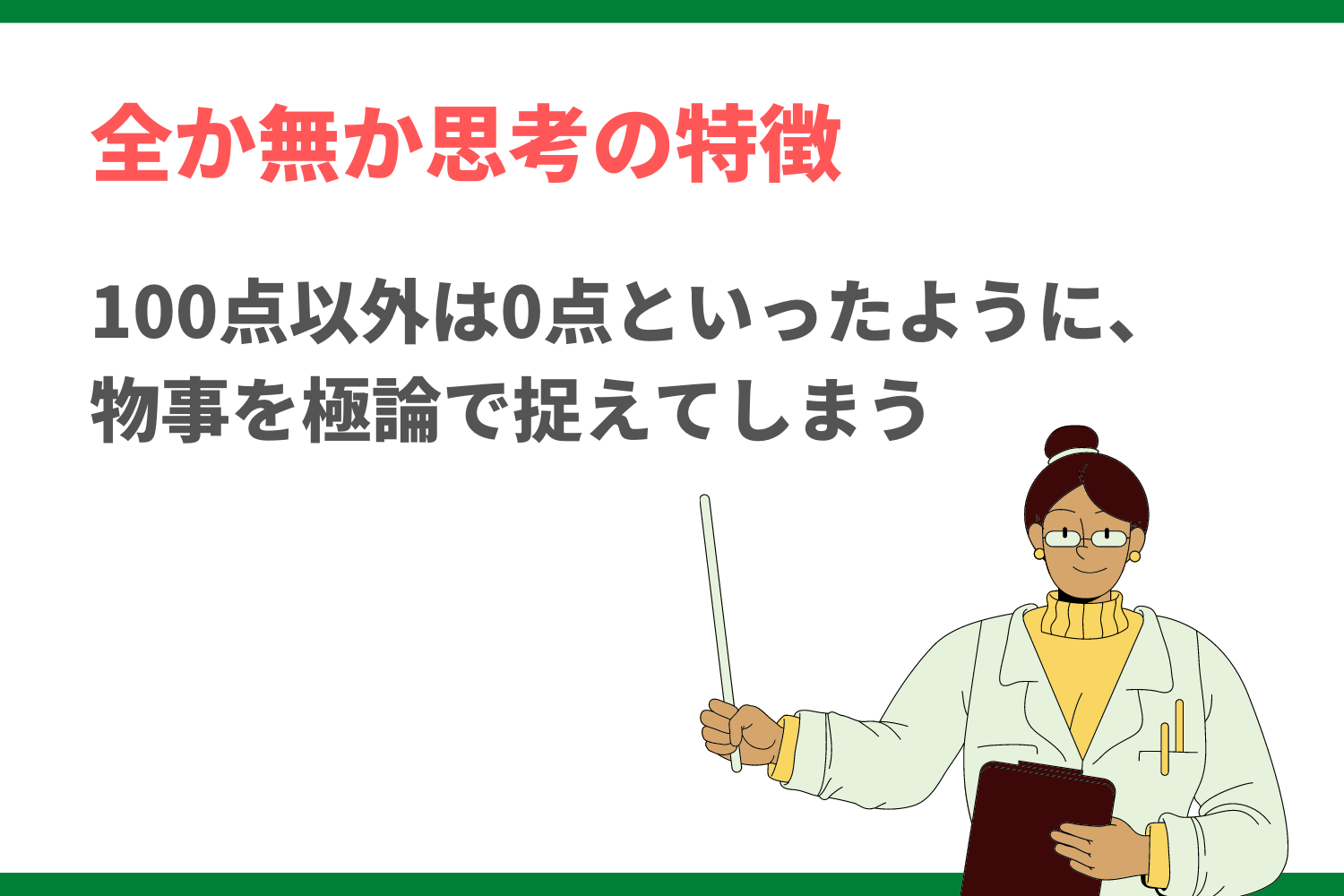
全か無か思考の問題点
物事を白か黒の両極端で捉えてしまう、全か無か思考。この思考パターンに陥ると、2つの問題が起こります。
自己評価が下がる
ひとつは、自己評価が下がること。
「100点以外は、すべて0点と捉えてしまう」というのは、本人からすれば、失敗体験が増えるということです。
例えば、今日も仕事でミスをしてしまった、やりたいことが全部できなかった、全力を出し切れなかったといったように。
物事を全か無か思考で捉えると、うまくいかないことばかりに意識が向きます。
実際には、ミスをしなかった仕事、できたこと、力を発揮した部分があったはずなのに、そういうことを無視してしまう…。
その結果、自分のなかでは、失敗に感じた経験だけが積み重なっていき、自己評価が下がってしまうのです。
劣等感を抱きやすくなる
自己評価が下がると、他人と比べて、自分を低く見積もるようになります。
「自分だけがうまくいっていない」「自分はダメな人間だ」といったように、他人よりも、自分が能力のない存在に思えてしまいます。
こうなると、劣等感を抱きやすくなり、何かにつけて落ち込みやすくなってしまうのです。
これが、全か無か思考のもうひとつの問題点です。
全か無か思考を修正する方法

あなたの落ち込みやすい原因が全か無か思考にあるのならば、思考パターンの修正方法を身につけたほうが良いでしょう。
ここからは、全か無か思考の修正方法について、紹介します。
偏った考え方に気づく
全か無か思考を修正するには、落ち込むできごとがあった時に、偏った思考パターンに陥っていないか、気づくことが必要です。
というのも、「偏った思考パターン」というのは、自分のなかに根づいているので、何かできごとがあると、自動的に頭に浮かぶようになってしまっているからです。
心理学では、これを「自動思考」と言います。
自動的に頭に浮かぶ考えであるため、意識しないと、修正はおろか、全か無か思考に陥っていることにさえ気づくことができません。
例えば、「仕事上で付き合いのあるクライアントに対して失礼な態度をとってしまい、先方を怒らせてしまった」としましょう。
この時、全か無か思考に陥ると、「取り返しのつかないことをしてしまった」「もうおしまいだ」などという考えが頭に浮かび、ひどく落ち込んでしまうものです。
落ち込むできごとがあった時には、まずは「偏った思考パターン」に陥っていないか、意識してみることが重要です。
中途半端な自分を受け入れる
「偏った思考パターン」に気づくことができたら、次は、自分ができている部分を振り返ってみましょう。
たったひとりのクライアントを怒らせてしまったとしても、まじめに仕事をしている人なら、普段は誠実な態度でクライアントと接することができていたり、ほかのクライアントとは良好な関係を築けていたりするものです。
あるいは、その日は、たまたま調子が悪くて、体調が悪いなりに精一杯やった、という自分なりの言い分があるかもしれません。
いずれにしても、気持ちの落ち込みを防ぐには、「完璧にできなかった」ことではなく、自分の「達成したこと」「努力したところ」「良い部分」に注意を向けることが必要です。
結果が中途半端であっても、自分なりに良くやれていると思えれば、気持ちの落ち込みを防ぐことができるものです。
落ち込みにくくなるには、「中途半端な自分」を受入れることが大切です。
中途半端でも満足感が得られることを知る
第3のステップは、「完璧にできなければ、自分も満足できないし他人も満足してくれない」という幻想をなくすことです。
全か無か思考に陥りやすい人は、何に対しても完璧を求めがちです。
ミスは許されない、妥協してはいけない、模範的であるべきといったように。
そのため、少しでもうまくいかないと、自分を責めたり、自罰的になったりして、落ち込んでしまうのです。
しかしながら、物事を完璧にやり遂げることと、自分や他人の満足感というのは、比例しないものです。
例えば、クライアントに提出する書類であれば、精度の高い文章表現であることよりも期限を守れることのほうが先方に喜ばれます。
家族のために料理をするのであれば、味がおいしいほうが喜ばれますが、家族からすると作ってもらうだけで満足感が湧くものです。
このように、物事の完成度と満足感は、必ずしも比例しないのです。
中途半端でも満足感が得られることを知れば、100点がとれなかったとしても、気持ちを落ち込まさずに、結果を受入れることができようになるでしょう。
柔軟な思考ができると、楽に生活できる
今回は、全か無か思考を説明するとともに、落ち込みにくい考え方に修正する方法について、説明しました。
全か無か思考を防ぐには、落ち込むできごとがあった時に、まずは「偏った思考パターンに気づくこと」、次に「できている部分を振り返り中途半端な自分を受け入れること」、それから「中途半端でも満足感が得られると知ること」という3つのステップをおこなってみましょう。
物事を極論で判断せず、柔軟な思考ができれば、自分のおこないに寛容になれ、いまよりも楽に生きられるようになります。
落ち込んでばかりでつらい生活になっているのだとしたら、自分の思考パターンを修正してみてはいかがでしょうか。